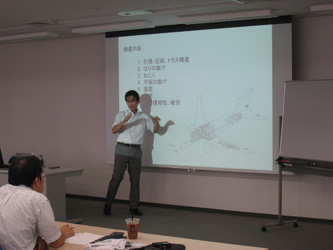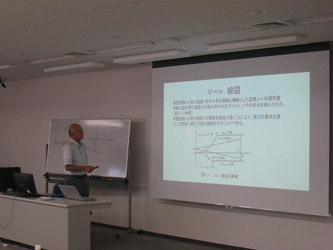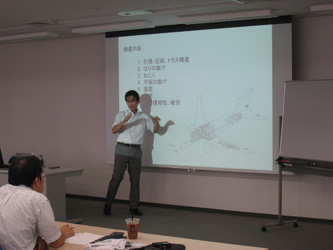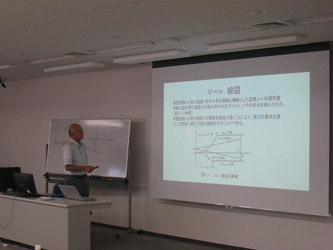第4回夏の学校 −複合材航空機設計入門−
期間:2017年8月22日(火)〜26日(土)
場所:金沢工業大学・虎ノ門キャンパス・11階1111講義室
参加者:14名
| 日程 | 9:30-11:00 | 11:30-13:00 | 14:00-15:30 | 16:00-17:30 |
| 8/22 | 火 | 連続体力学の基礎 |
| 8/23 | 水 | 複合材料の力学 |
| 8/24 | 木 | 構造力学 |
| 8/25 | 金 | 有限要素法解析 | 複合材航空機構造設計 |
| 8/26 | 土 | KMAPによる航空機概念設計演習 |
連続体力学の基礎(担当:岡部朋永(東北大学))
本項目では,航空機設計に欠かすことの出来ない連続体力学の基礎をポイントを絞って説明する.特に,理論の構成上欠かすことのできないテンソル解析,変形とひずみ,応力,保存則について具体的に手を動かしながら学習する.これにより,固体力学あるいは流体力学の基礎式を自ら導出することが出来るようになる.また,連続体力学適用の実例として,実際の機体設計の現場にて用いられる有限要素解析をその定式化から具体的な計算の手順まで例題をもちいながら平易に説明する.
複合材料の力学(担当:田中基嗣(金沢工業大学))
本項目では,演習を交えながら「複合材料の力学」について理解を深めることを目指す.まず,異方性材料の応力とひずみの関係から,一方向繊維強化複合材料平板における変形について導出する.次に,一方向繊維強化複合材料の繊維方向ヤング率・ポアソン比・繊維直角方向ヤング率・せん断弾性率・線膨脹係数に関する複合則について学習する.さらに,積層板理論により剛性行列を導出し種々の積層板の変形について理解するとともに,層間に生ずる応力について説明する.最後に,複合材料積層板の破壊力学モデルについて解説し,複合材料積層板の破壊を予測する手法について学ぶ.
構造力学(担当:横関智弘(東京大学))
本講義では,航空機構造設計の基礎となる構造力学について,各種構造様式を意識しながら,引張・圧縮,曲げ,ねじり,平板などの基礎式を学ぶと共に,その応力解析例に触れることで構造解析に関する理解を深めることを目指す.後半では,航空機構造設計に必要な座屈,構造信頼性,疲労,損傷許容に関する知識を得ながら,軽量構造を実現するための設計法や構造様式について学ぶ.
有限要素法解析(担当:長嶋利夫(上智大学))
有限要素法とは,微分方程式で表わされる物理現象について,任意形状を有する解析対象領域を「要素」と呼ばれる小領域に分割して,要素に設けられた「節点」位置での物理量を求める数値的近似解法の一つである.有限要素法は,構造力学,流体力学,伝熱工学などにおける数値シミュレーション手法として広く用いられている.本講義では,構造物の応力解析に用いられる有限要素法に関連する,数学,力学,数値計算法,解析手順などについて解説する.
複合材航空機構造設計(担当:廣瀬康夫(金沢工業大学))
本項目では,航空機の構造設計に関する基本的な事項について講義を行う.すなわち,航空機に作用する荷重やV−n線図について解説し,航空機の主要構造である主翼構造,胴体構造,尾翼構造について概要を説明する.構造解析に関しては,主翼ボックス構造の構造解析,胴体与圧荷重,主翼桁構造張力場の解析について例題を用いて説明する.また,複合材料の特性,航空機構造への適用に当たっての設計上の留意点について実機例に基づいて説明する.さらに,大型複合材構造の工程上の課題と今後の動向について説明し,一体成形に適した複合材料の特長を生かした新構造様式について内外の研究例を紹介する.
KMAPによる航空機概念設計演習(担当:片柳亮二(金沢工業大学))
本項目では,航空機の機体諸元(大きさ,重量)が飛行能力(乗客数と飛行距離)とどのような関係にあるのかをまず理解する.次に,実際に飛行している旅客機について,機体諸元と飛行能力の検証を通して理解を深める.一応の基礎知識を学んで後,話題提供として,“そもそも揚力はどのように発生するのか”について考える.飛行機が今日の発展を遂げるのに500年の年月がかかった歴史を概観する.次に,安定に飛行できる原理についての基礎を学ぶ.これは尾翼の設計に関連する.水平尾翼が後方にある通常機と前方にある先尾翼機との違いについても考える.最後に,KMAP(ケーマップ)ソフトを用いて,乗客数,航続距離,離着陸滑走路長の要求を満足する旅客機の概念設計の演習を実施する.
写真集